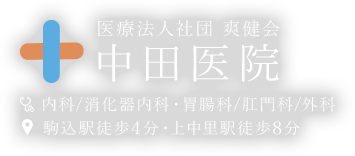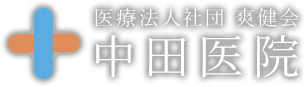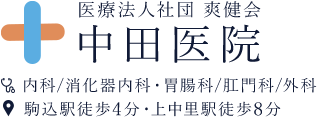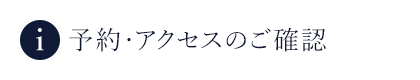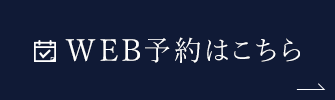以下のような症状はありませんか?

- 排便できない状態が3日以上続いている
- 腹部に強い痛みが起こる
- 市販の下剤を飲んでも便秘が解消しない
- 便秘に伴って吐き気を催す
- 排便時に肛門が切れて出血が起こる
- 便に血が混入している
- 排便後も便が出し切れていない感覚がある
目次
便秘とは
便秘とは、3日以上にわたって排便がない状態です。
また、排便回数に特に問題がなくとも、強くいきまないと排便できない状態、排便できても残便感を覚える状態も便秘に該当します。
便秘の症状が重症化すると腸内で異常が起こり、大腸疾患などを招く恐れもあるため、慢性化している場合は早めに当院までご相談ください。
便秘の原因
便秘の原因は個人差がありますが、大きく分けて「弛緩性」「痙攣性」「直腸性」の3種類の機能性便秘と、器質性便秘があります。
運動不足や過剰なダイエットによる弛緩性便秘
腸管の緊張が緩み、蠕動運動が低下することで起こる便秘です。
便が大腸内に長く滞留することで、水分を必要以上に吸収し、硬く太くなり排便時に痛みを感じるようになります。 便秘において最も起こりやすいタイプで、特に高齢者や女性に好発します。排便時の痛みのほか、残便感や腹部の張り、食欲低下、肌荒れ、肩こり、イライラなどの症状を示します。
ストレスなどによる痙攣性便秘
環境の変化やストレスなどにより自律神経が失調し、腸が痙攣した状態になることで起こる便秘です。
ウサギの糞便のようなコロコロした小さな便が出るようになります。 残便感や食後の下腹部痛などが起こります。
また、便秘と下痢が交互に何度も起こる特徴があり、過敏性腸症候群の便秘型・混合型もこのタイプです。 改善のためには原因を取り除くことが必要です。
高齢者に好発する直腸性便秘
直腸の感度が低下して便意を感じづらくなり、便が溜まって排便が難しくなる便秘です。
寝たきりや高齢者によく認められますが、その他にも、痔による痛みや羞恥心から排便を何度も我慢してしまうと起こります。
疾患が原因となる器質性便秘
腸閉塞、腸管の癒着、大腸がんなどの器質的異常により、便の通過が障害されることで起こる便秘です。
下剤を服用して無理に排便しようと、腸管に穴があく穿孔が起こることもあるため注意が必要です。
便秘に関連する疾患
代表的な疾患
- 痔
- 裂肛
- 直腸脱
- 憩室性疾患
- 宿便
排便時の強いいきみが原因となる「痔」
排便時に無理にいきむと、肛門周囲の靜脈が圧迫され、痔になる可能性があります。頻度は低いですが、直腸が肛門外に脱出する直腸脱を起こす可能性があります。 痔による痛みから排便を我慢してしまうと、便秘が悪化し、合併症を招く恐れもあるので注意しましょう。
手術を行うこともある「大腸憩室症」
大腸憩室症とは、大腸壁の一部が5~10mmほど外側に向かって飛び出す疾患です。開口部が2cm以上となることもあります。 憩室自体では症状が起こりませんが、憩室内を走る血管が損傷して出血する大腸憩室出血、憩室内で細菌が装飾して炎症が発生する大腸憩室炎など、合併症が起こる可能性があります。重症化した場合、内視鏡的止血術が治療の第一候補となります。 内視鏡的止血術が適応しない場合、あるいは失敗した場合、動脈塞栓術を実施します。これも失敗した場合、大腸切除術を実施します。
妊婦や高齢者に好発する「宿便」
宿便とは、直腸とS状結腸・下行結腸で便が硬くなり、他の便の通過に障害が起こった状態です。宿便が起こった場合、腸の痙攣や痛みが発生し、いきんでも便を出し切れなくなります。 水のような粘液や液体のような便が閉塞した部分の周りから漏れ出て、下痢と勘違いする方もいます。 宿便は、普段からあまり動かない妊婦や高齢者、バリウムを用いたレントゲン検査や浣腸を行った方によく起こります。
便秘の検査
 問診にて、便の状態や腹痛の有無、生活習慣などを伺います。
問診にて、便の状態や腹痛の有無、生活習慣などを伺います。
問診後、腸内にガスや便がどの程度溜まっているかを調べるために腹部レントゲン検査を行ったり、大腸がんなどの疾患を発症していないか調べるために大腸カメラ検査を行ったりします。 また、腸の捻じれの有無を確認し、これらの情報をもとに適切な治療を行います。
便秘の治療法
便秘の治療は食生活の見直しが中心となります。食物繊維や水分をしっかり摂っていただきます。
また、適度な運動の習慣化や適切な排便習慣を身に着けましょう。ストレスを溜めないように意識することも大切です。
毎日3食欠かさず食べる
毎日3食しっかり食べましょう。
特に朝食は排便を促すので、毎日欠かさず摂るようにしてください。
食物繊維や水分をしっかり摂る
食物繊維は腸の蠕動運動を活発化させ、排便を促します。
食物繊維を豊富に含む食品には、イモ類や穀物、豆類、寒天、ひじき、果物などが挙げられます。 また、水分もしっかり摂りましょう。水分が不足した状態だと便が硬くなり、排便がスムーズに行えません。便が水分を適切に吸収すると、便のカサが増し、腸が刺激されて便意を催しやすくなります。
毎朝、冷水か牛乳を1杯飲むとその日は便意を催しやすくなります。
適度な運動を習慣化する
便秘の原因には運動不足もあります。
筋力や体力の低下により蠕動運動が低下することで起こる弛緩性便秘は、腹筋など腹部の筋肉を高める運動を行うと改善が期待できます。
運動が億劫な方は、腹部を毎日マッサージすることで腸が刺激され、排便がスムーズに行えるようになります。
便秘が改善しない場合は当院までご相談ください
 便秘の治療薬には刺激性下剤や浸透圧性下剤などがあり、この2つは病院で処方されることも多く、市販化もされています。刺激性下剤は高い効果を持つ一方、依存してしまうケースがよくあり、長期間にわたって使い続けると効果が弱まっていきます。
便秘の治療薬には刺激性下剤や浸透圧性下剤などがあり、この2つは病院で処方されることも多く、市販化もされています。刺激性下剤は高い効果を持つ一方、依存してしまうケースがよくあり、長期間にわたって使い続けると効果が弱まっていきます。
市販薬で効果が薄まった場合も、医療機関で処方される便秘の種類にあった適切なお薬により改善が期待できます。 消化器内科では、新たな作用の仕組みがあるお薬も処方できます。こうした新薬はこれまでのお薬に比べ、耐性が付きにくいというメリットがあります。
便秘が続いている方、便秘に伴って別の症状も起きている方、従来の治療薬では下痢が解消しない方は、当院までご相談ください。