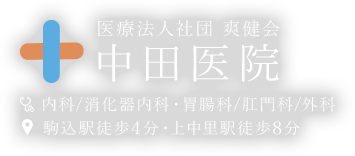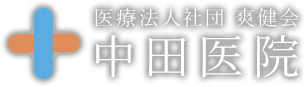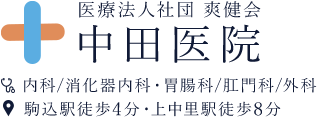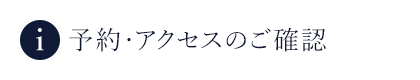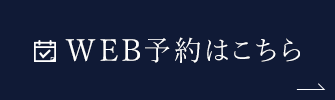以下のような症状はありませんか?

- 腹痛が起きている
- お腹がゆるくなった
- 排便回数が多い
- 水っぽい便が出る
- 血が混ざった便が出る
- 黒っぽい見た目の便が出る
- 粘液が混ざった便が出る
- 下痢に加え、発熱も起こる
目次
下痢とは
下痢とは、腸で水分がしっかり吸収されず、水のような便が出る状態です。
原因には、ストレスや暴飲暴食、食中毒などの感染症などが挙げられます。
下痢の原因
- 暴飲暴食
- ストレス
- 細菌感染
- 食あたり
- 食物アレルギー
- 腸の炎症や腫瘍
- お薬の副作用
ストレスや冷えにより自律神経が失調し、腸の蠕動運動が亢進し、便の水分がしっかりと吸収されない状態で排泄されるようになることで、下痢が起こることがあります。また、生食あるいは消費期限が切れた食べ物を食べたことにより、細菌感染が起こり、下痢となることもあります。
魚介や小麦など食物アレルギーを持つ方は、アレルゲンとなる食べ物を食べることで腸管内の分泌液が必要以上に分泌され、下痢が起こることがあります。その他、解熱鎮痛剤などのお薬を服用し、副作用により腸粘膜に異常が発生することが下痢の原因となることもあります。
下痢が1ヶ月以上続く場合、慢性下痢と診断されます。
この場合、神経性あるいは深刻な疾患が原因となることもよくあるので、早めに当院までご相談ください。
下痢に関連する疾患
代表的な疾患
- 急性胃腸炎
- カンピロバクター腸炎
- 急性虫垂炎(盲腸)
- 過敏性腸症候群
- 大腸ポリープ
- 大腸がん
- 潰瘍性大腸炎
- クローン病
急性胃腸炎とは、ウイルスや細菌などの病原体の胃腸への感染が原因となる疾患です。
ノロウイルスをはじめウイルスの感染が原因となるものは「ウイルス性胃腸炎」と呼ばれ、カンピロバクター菌やサルモネラ菌などの細菌の感染が原因となるものは「細菌性胃腸炎」と呼ばれます。 下痢が頻発し、血便なども続く場合、大腸がんが疑われます。大腸がんは、初期は自覚症状が乏しいですが、悪化に伴って血便や下痢症状が悪化し、腫瘍が大きくなるとしこりがはっきりと確認できるようになります。
また、腹部の不快感や下痢が数ヶ月以上にわたって続いているにもかかわらず、検査で器質的異常が発見されない場合、過敏性腸症候群の診断となります。ストレスを受け大腸の運動機能にトラブルが発生し、腸の蠕動運動が亢進したり痙攣したような状態になったりすると、強い痛みを示します。
下痢の検査
 直近3ヶ月のうち1ヶ月で3日以上腹痛が続いた、あるいは腹部の不快感が起こった場合、この症状が排便によって治まったか、症状が出てから排便回数が変わったか、症状が出てから便の形が変わったかが基準となります。
直近3ヶ月のうち1ヶ月で3日以上腹痛が続いた、あるいは腹部の不快感が起こった場合、この症状が排便によって治まったか、症状が出てから排便回数が変わったか、症状が出てから便の形が変わったかが基準となります。
大腸カメラ検査、大腸造影検査、便検査、血液検査、尿検査などを実施し、異常が発生している部位を特定します。また、必要に応じて腹部超音波検査や腹部CT検査を行うこともあります。こうした検査により、炎症や悪性腫瘍の有無、寄生虫や細菌の感染有無を確認できます。
なお、検査によって病変など原因が発見されない場合、過敏性腸症候群と診断されます。
下痢の治療法
下痢は一時的なものもありますが、慢性化することもあります。下痢に加え、激しい腹痛、嘔吐、発熱症状を示す場合、すぐに医療機関を受診しましょう。
便の状態や期間、便の色などの情報も診断に役立つため、診察時に医師にお伝えください。 治療は薬物療法が中心となり、腸の働きを抑制する効果や殺菌効果がある下痢止めを使います。また、腸粘膜の保護や腸の水分吸収量を増やすお薬を使用することもよくあります。その他、腸内の環境を改善する整腸剤を使用することもあります。
下痢の原因が潰瘍性大腸炎やクローン病の場合、完治させる治療法が確立されていませんが、薬物療法により症状を落ち着かせることはできます。大腸がんが原因の場合、早期に発見できれば内視鏡により腫瘍を切除できることもありますが、進行している場合は放射線治療や抗がん剤治療、あるいは腸管を切除することもあります。