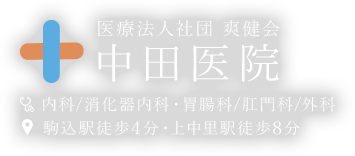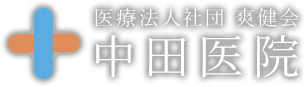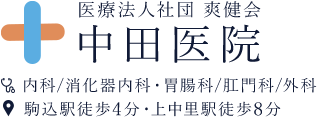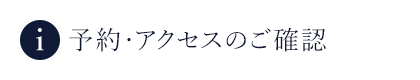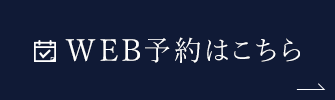慢性胃炎
慢性胃炎とは、胃粘膜に慢性的な炎症が発生することで、胃粘膜が萎縮してしまう疾患です。
慢性胃炎で起こる主な症状には、胃もたれや胃の不快感、腹痛、食欲不振、胸やけや吐き気などがありますが、中には無症状の方もいらっしゃいます。
発症にはピロリ菌が深く関与しており、塩分やアルコールの過剰摂取、喫煙、ストレスなどの要因が加わることで、慢性胃炎が増悪します。
慢性胃炎の検査、種類
検査では胃カメラ検査を行います。
慢性胃炎は下記のように4つの種類に分類され、合併することもあります。
- 表層性胃炎
- びらん性胃炎
- 肥厚性胃炎
- 萎縮性胃炎
萎縮性胃炎は、増悪すると胃粘膜が腸粘膜に似た状態(腸上皮化生)に変性し、この状態は胃がんに繋がりやすいです。
萎縮性胃炎はピロリ菌が原因となり、慢性胃炎と同様の症状を示します。萎縮が進行すると、胃酸や胃粘液を分泌する固有腺が減少し、胃もたれなどの症状を示します。
治療
一度萎縮した粘膜を元に戻すことは難しいです。
胃酸や胃粘液の分泌量が減少するため、以前は脂っこいものを好んでいた方が、あっさりしたものを好むようになったという話もよく伺います。
治療は対症療法となり、お薬を用いた治療を行います。胃の不快感や胃もたれを強く示す場合は、胃粘膜保護薬や消化管運動機能改善薬を使用します。胸やけや吐き気を強く示す場合は、酸分泌抑制薬を使用します。ピロリ菌の感染が原因となる場合、除菌治療に成功することで症状の解消が期待できます。
胃潰瘍/十二指腸潰瘍
潰瘍とは粘膜下層にまで炎症が及び、粘膜がえぐれた状態です。
腹痛症状を示し、出血するとタール便が排泄されます。潰瘍を繰り返すと胃や十二指腸が狭窄し、通過障害が発生します。原因には、暴飲暴食やストレス、タバコ、消炎鎮痛剤などのお薬の副作用、ピロリ菌感染などが挙げられます。治療では、従来は手術を行うことが多かったのですが、昨今は薬物療法で解消できるようになっています。使用するお薬は、胃粘膜保護剤や制酸剤などがあります。出血量が多く吐血する場合、すぐに内視鏡を用いて止血処置が必要です。
潰瘍が悪化し、粘膜に穴があく穿孔が起こった場合、手術を行います。また、ピロリ菌によって潰瘍が起きている場合、除菌治療に成功することで再発リスクを大幅に低下させることが可能です。
過敏性腸症候群
消化管、なかでも腸機能に異常が起こることが原因の疾患です。
内視鏡検査などで器質的病原が発見されないにもかかわらず、腹部の不快感や腹痛、便秘、下痢などの消化器症状が何度も起こります。日本では、全人口の13%ほどの方がこの疾患を発症していると考えられています。症状の内容により、便秘型、下痢型、混合型に分類されます。消化機能は自律神経によってコントロールされているため、ストレスなどがきっかけになり、症状が起こります。よくある例として、試験や会議など重要な場面で、ストレスがかかると腹痛が起こります。
治療は、食事などの生活習慣の改善指導、消化管機能調節薬などの薬物療法を行います。
機能性ディスペプシア
胃機能に異常が発生することが原因の疾患です。
内視鏡検査などで器質的病原が発見されないにもかかわらず、胃もたれや心窩部痛、早期膨満感などの症状が何度も起こります。日本では、全人口の10~20%ほどがこの疾患を発症していると考えられています。胃機能は自律神経がコントロールしているため、ストレスがかかると自律神経が失調し、症状が起こります。また、生活習慣の乱れや胃酸の分泌過多、ピロリ菌感染なども関わっていると言われています。
治療は薬物療法が行われ、酸分泌抑制薬、消化管運動機能改善薬のほか、抗うつ薬や抗不安薬、漢方薬などを使用します。
潰瘍性大腸炎
免疫異常が原因の疾患で、大腸粘膜にびらんや潰瘍が発生します。
よくある症状としては、腹痛や下痢、粘血便などが挙げられます。原因は明確になっておらず、完治させる治療法も確立されていないため、厚生労働省より難病指定を受けています。治療には公費が負担されます。症状が治まる寛解期と症状が起こる再燃期を繰り返すため、寛解期になるべく早く導入し、その状態を保つことが必要です。 治療では薬物療法を行います。
なお、一部の方は薬物療法では効果が現れず、重症化して外科的治療を行うことになります。発症から10年以上経過し、大腸がんを合併することもあります。
アニサキス
アニサキスは魚介類に棲みつく寄生虫です。
生あるいは十分に火を通さない状態で食べた後、数時間経過すると激しい腹痛や吐き気を示します。アニサキスの成虫はイルカや鯨などの哺乳類に寄生しますが、幼虫は普段よく食べるアジやサバ、サケ、イカなどの筋肉や内臓に寄生します。アニサキスの幼虫が寄生した状態で、生あるいは十分に火を通さない状態で食べてしまうと、アニサキスが胃の内部に侵入し、胃粘膜に刺さり、激しい腹痛症状を示す胃アニサキス症が起こります。
バレット食道
胃と食道の境目から食道下部までの食道粘膜は扁平上皮という粘膜で覆われています。食道バレットとは、慢性的な胃酸などの胃の内容物の逆流によりこの扁平上皮が胃粘膜を覆う円柱上皮に変性した状態です。
バレット食道そのものは命を落とすようなリスクはないものの、食道がんの発生母地となるため、注意しましょう。バレット食道を発症している場合、発症していない方と比べると食道がんの発生率が30~60倍ほど高くなると言われています。バレット食道に起こるがんは、日本でよく見られる食道扁平上皮がんと違い、食道腺がんと呼ばれる特殊な種類のもので、別名「バレット食道がん」と呼ばれることもあります。
がん化する経過をまとめると、はじめに逆流が起こって逆流性食道炎を発症し、それがバレット食道へと繋がり、やがて食道腺がん(バレット食道がん)を発症します。 欧米では逆流性食道炎の発症が増加傾向にあり、それに伴ってバレット食道やバレット食道がんも増加していると言われています。日本においても食生活の欧米化を背景に、逆流性食道炎が増加傾向にあるため、将来的にはバレット食道の発症数も増えていくと予測されています。
脂肪肝・アルコール性肝障害
脂肪肝とは、肝臓細胞に脂肪が溜まることにより、肝機能に異常が起こる疾患です。
男性に好発しますが、最近では女性でも50歳以上の方の発症が増えてきています。 脂肪肝の原因は、従来は、過剰な飲酒、ウイルス性肝炎(B型肝炎やC型肝炎など)がほとんどでしたが、昨今はこれら条件に当てはまらない方でも脂肪肝を発症することが判明しました。これは非アルコール性脂肪肝(NASH)というもので、肥満(メタボリックシンドローム)や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病に合併します。
アルコール性肝障害は、日頃からアルコールを飲んでいる方に起こる疾患です。毎日、多量のアルコールを摂取している方は、痩せているように見えても、肝臓に脂肪が溜まり、炎症が発生することがあります。 脂肪肝・アルコール性肝障害の患者様は過剰にアルコールを摂取した後、重症のアルコール性肝障害に繋がり、命を落とす可能性があります。 また、治療を受けずにそのままにしておくと、肝硬変や肝がんに繋がることもあります。