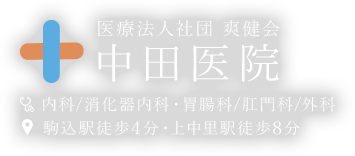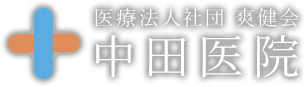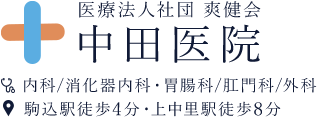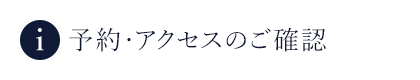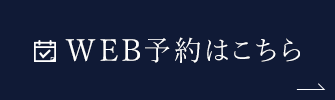生活習慣病とは
 生活習慣病とは、暴飲暴食や偏食、運動不足、飲酒、喫煙など、乱れや生活習慣を長年にわたって続けることで起こる慢性疾患の総称です。
生活習慣病とは、暴飲暴食や偏食、運動不足、飲酒、喫煙など、乱れや生活習慣を長年にわたって続けることで起こる慢性疾患の総称です。
主な疾患には、高血圧や糖尿病、脂質異常症(高脂血症)、高尿酸血症(痛風)などが挙げられます。動脈硬化の進行を招き、心筋梗塞や脳卒中などの深刻な疾患や合併症に繋がる恐れがあります。生活習慣を改善し、生活習慣病の進行防止・予防に努めましょう。
健康診断で異常が指摘された場合
自覚症状がなくとも治療を受けましょう
 生活習慣病は自覚症状がほとんどなく、医療機関に受診した頃には重症化していることが多いです。
生活習慣病は自覚症状がほとんどなく、医療機関に受診した頃には重症化していることが多いです。
高血圧・糖尿病・脂質異常症は合併リスクが高く、各数値がさほど異常値を示していなくとも動脈硬化の進行を招くとされています。健診結果では各数値がさほど異常値を示していなく、自覚症状が出ていない場合も、急に心筋梗塞や脳卒中を発症する恐れがあり、特に肥満の方はリスクが高いため注意が必要です。
こうした疾患の進行を防ぐため、症状を自覚していない方も、健康診断で異常が見つかった場合は、早めに検査を受けて治療に取り組みましょう。疾患が早期の場合、食事療法や運動療法で効果が期待できます。なお、こうした治療でも効果が十分でない場合、薬物療法を行います。
受診をお勧めする方
- 運動不足
- 暴飲暴食・偏食
- 食事時間が一定でない
- 間食することが多い
- 濃い味付けを好む
- 揚げ物など脂っぽいものを好む
- インスタント食品や加工食品、ファストフードを食べることが多い
- 喫煙習慣がある
- 飲酒習慣がある
- 糖分を含む飲み物を好む
(ジュース、炭酸飲料、エナジードリンク、砂糖入りのコーヒーなど) - 睡眠不足
- ストレス過多
- 車での移動が多い
- 20歳から体重が10kg以上増えた
- 健康診断で異常や要精密検査と指摘された
- 健康診断で複数の項目がグレーゾーンとなっている
- 生活習慣病の発症リスクが高まる40歳以上
…など
代表的な生活習慣病
糖尿病
糖尿病は高血糖状態が慢性化する疾患です。
血糖値とは、血中に含まれるブドウ糖濃度で、全身のエネルギーとして代謝されます。血糖値が高い状態が続くと、全身の血管に大きなダメージが加わり続け、重大な合併症を招く可能性があります。原因は2つに大別され、血糖値を下げるインスリンの作用低下、あるいは分泌量自体が減少することです。
高血圧
高血圧の状態は血管に強い圧力が常にかかっており、動脈硬化の進行を招きます。また、脳出血の最大の要因とも言われています。
血圧は、直前の食事や運動、緊張などが影響し、1日の中でも大きく変動するため、ご自宅にて定期的に計測しておきましょう。ご自宅に血圧計がない場合、健康診断などで定期的に測定し、高血圧になっていることが分かった場合、早めに当院までご相談ください。
脂質異常症(高脂血症)
脂質異常症とは、血中のLDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪が高い状態(高脂血症)、あるいは血中の余分なコレステロールを回収して肝臓に戻すHDLコレステロールが少ない状態です。
悪化しても自覚症状が乏しく、動脈硬化が進んで血管の狭窄・閉塞を招く可能性があります。そのため、健康診断などで異常値を示した場合、早めに検査・治療を受けましょう。
高尿酸血症(痛風)
尿酸の血中濃度が高い状態が持続する疾患です。過剰になった尿酸が結晶化し、関節に沈着して炎症が発生したものが痛風です。
尿酸値を低下させるためには食事療法と運動療法、こまめな水分摂取が大切です。また、激しい運動は尿酸値の上昇を招くため、適度な有酸素運動を行いましょう。状態次第では薬物療法を行うこともあります。
メタボリックシンドローム
メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満に加え、血圧、血糖、脂質のうち2つ以上が異常値を示す状態です。
この状態では、各数値がさほど悪くなくても動脈硬化の進行を招くため、急に心筋梗塞や脳卒中が起こる可能性があります。肥満や高血圧、糖尿病、脂質異常症は、同じ生活習慣の乱れから発症することが多いため、合併リスクが高いです。内臓に過剰な脂肪が溜まる内臓脂肪型肥満ではそのリスクが上昇するため、特にメタボリックシンドロームの方は気をつける必要があり、早期発見・早期治療が欠かせません。
脳卒中や心筋梗塞などの重大な疾患の発症を防ぐためにも、以下の診断基準に近い状態の方は一度当院までご相談ください。
メタボリックシンドロームの診断基準
必須項目
- 内臓脂肪型肥満
立位でリラックスした状態で、ウエスト周囲径(おへその高さの腹囲)を測ります。
男性では85cm以上、女性では90cm以上の場合、内臓脂肪型肥満の診断となります。
選択項目
内臓脂肪型肥満に加え、血圧、血糖、脂質のうち2つ以上が異常値を示すとメタボリックシンドロームの診断となります。
- 血圧
収縮期血圧(最大血圧)130mmHg以上、または拡張期血圧(最小血圧)が85mmHg以上、あるいはその両方が該当する。 - 血糖
空腹時血圧が110mg/dL以上 - 脂質
中性脂肪値が130mmHg、またはHDLコレステロール値が40mg/dL未満、あるいはその両方に該当する。
「肥満症」の基準
 肥満の判断にはBMI(Body Mass Index)という体格指数が用いられます。
肥満の判断にはBMI(Body Mass Index)という体格指数が用いられます。
BMIは、身長と体重の比率から算出されます。
以下に当てはまる方は肥満と診断されます。
- BMIが25以上であり、健康被害が起きている
- 健康被害は起きていないものの、健康診断などで内臓脂肪量の指摘を受けた
BMIが25以上の状態は様々な疾患が起こる可能性があるため要注意です。
GLP-1
GLP-1(痩せホルモン)とは
GLP-1は膵臓に作用してインスリンの分泌を促し、血糖値の上昇を抑える効果があるホルモンです。
また、満腹ホルモンとも呼ばれており、食欲を抑える効果もあります。健康な方は、食事を摂ると小腸からGLP-1ホルモンが分泌され、脳に信号が伝わって満腹感が得られ、食べ過ぎを防ぎます。さらに、GLP-1ホルモンは、腸機能や胃酸の分泌を抑える効果もあるため、消化に時間がかかり、食欲を抑えられます。
GLP-1ホルモンの分泌量には個人差があり、分泌量が多い方は痩せやすい体質であり、反対に分泌量が少ない方は太りやすい体質となります。そのため、肥満症の方に、GLP-1受容体作動薬を使用すると、食欲を抑えられ、体質の改善にも繋がります。
日本では、従来2型糖尿病の治療薬として使用されてきましたが、昨今は肥満治療でも活用されることが多くなっています。
GLP-1受容体作動薬の内服薬
日本の医療現場においては、GLP-1受容体作動薬は、サクセンダ、オゼンピック、ビクトーザなど注射薬を使用することが主流でしたが、注射を苦手な方も多いので躊躇される方もいました。なお、昨今はリベルサスという内服タイプのGLP-1受容体作動薬が登場しており、以前よりも治療を受けやすくなっています。