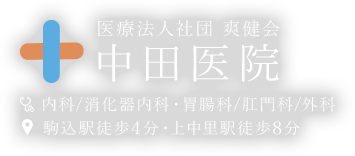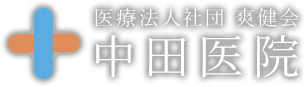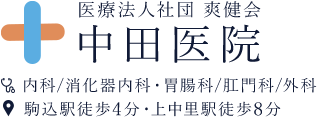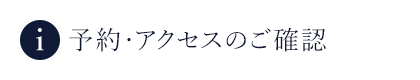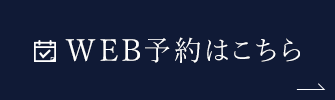食欲不振の関連項目
体重減少の関連項目
食欲不振とは
 食欲不振とは、食欲が湧かない、少量しか食べられないなどの状態を言います。
食欲不振とは、食欲が湧かない、少量しか食べられないなどの状態を言います。
消化器は脳と深く関係しています。食べ物が胃に運ばれて消化され、そこから腸に送られると、脳の食欲中枢が刺激され、空腹を感じます。しかし、何らかの原因でこのメカニズムに障害が発生すると、食欲不振を起こす可能性があります。
食欲不振の状態が持続した場合、必要な栄養素が不足し、抵抗力が弱まります。また、栄養バランスも乱れて体調の悪化も招きます。食欲不振は、心身の疲労からくる一過性のものもありますが、疾患が原因となる慢性的なものもあるので、食欲不振が解消しない場合は当院まで一度ご相談ください。
食欲不振の原因
感染症やその他の疾患
瘍、十二指腸潰瘍、胃がん、食道がん、機能性ディスペプシア、過敏性腸症候群、肝臓疾患などの消化器疾患、腎臓疾患、心不全などの心臓疾患、脳腫瘍などの脳疾患、頭痛、電解質異常などが原因に挙げられます。また、風邪や気管支炎、インフルエンザ、肺炎などの感染症による体調不良、口内炎や虫歯、歯周病などの口腔障害も原因となります。
甲状腺機能低下症(橋本病)
慢性甲状腺炎や放射線障害によって甲状腺機能が弱まると、甲状腺ホルモンの分泌量が少なくなります。
甲状腺ホルモンは、全身の代謝をコントロールする働きがあるので、分泌量が低下すると、倦怠感や疲労感、食欲不振などの症状が起こります。
ストレス
心身にストレスがかかることで自律神経のバランスが乱れ、副交感神経の働きが低下し、食欲不振を招きます。
生活習慣の乱れ
食事時間の乱れ、運動不足、睡眠時間の不足などにより、自律神経のバランスが乱れると、食欲不振を招くことがあります。
また、過度な飲酒は、肝臓の大きな負担となり、食欲不振が起こる可能性があります。
食欲不振の原因となる主な消化器疾患
胃がん
胃がんは初期には自覚症状が乏しいですが、病状が悪化すると、胃機能が弱まり、食欲不振が起こります。
機能性ディスペプシア
胃炎や胃がんなどの器質的異常がないものの、多くの消化器症状を起こす疾患です。症状の1つに食欲不振があります。
慢性胃炎(萎縮性胃炎)
慢性胃炎はピロリ菌の感染が主な原因です。ピロリ菌に感染すると、胃炎膜にダメージが加わり、食欲不振が起こります。
胃・十二指腸潰瘍
胃粘膜・十二指腸粘膜が慢性的な炎症によって深く損傷した状態です。痛みや吐き気が起こりますが、胃の出口である幽門付近に潰瘍が発生すると食物の通過障害が起こり、食べ物が留まってしまうため膨満感や食欲不振が起こります。
食道がん
食道がんは初期には自覚症状が乏しいですが、悪化すると食物の通過を妨げ、食欲不振が起こります。
逆流性食道炎
胃酸が食道方向に流れ込むことで食道粘膜に炎症が発生する疾患です。胸やけや呑酸がよくある症状ですが、食欲不振を招くこともあります。
体重減少
 食欲はあっていつも通り食べているのに体重が減っていくことがあります。
食欲はあっていつも通り食べているのに体重が減っていくことがあります。
思い当たる原因がない体重減少は、疾患が原因で起きていることが疑われます。体重が急激に減少する場合、速やかに治療すべき疾患を発症していることもあるため、早めに医療機関を受診しましょう。
また、過剰なダイエットや運動により体重が減少した場合、栄養不足になっていることも考えられ、健康面・身体機能に支障がでる恐れがあります。
日常的な原因による体重減少
ダイエット
過度なダイエットは栄養バランスが崩れ、身体機能に支障が出る可能性があります。また、体重が増えることに恐怖を覚え、過剰な減量に取り組んでしまう神経性食欲不振症(拒食症)を起こす可能性もあります。健康な状態をキープするために、栄養をしっかり摂りましょう。
精神的ストレス
消化機能は自律神経によって制御されています。不安や緊張からくるストレスが過剰な場合、自律神経が失調し、消化機能が低下することで食欲不振や体重減少が起こります。また、ストレスが、逆流性食道炎や機能性ディスペプシア、過敏性腸症候群、下痢、便秘、腹痛などの原因となり、これらの疾患・症状によって体重減少に繋がることもあります。
エネルギーの過剰消費
激しい運動や過労による消費エネルギーが、食事による摂取エネルギーを上回り、体重減少が起こることがあります。この状態では、若い方でも骨粗鬆症のリスクが高まり、骨折しやすい状態となります。女性の場合は無月経が起こることも多いです。
進行がん
進行がんが原因となり、体重が減少することがあります。その他の症状は示さないことも多いので、気を付けましょう。
体重減少の原因となる主な疾患
神経性食欲不振症(拒食症)
適正体重を大幅に下回っているにも関わらず、太ることへの恐怖心や減量への脅迫的な追求心から、さらなる減量に取り組もうとする精神疾患です。
過度なカロリー制限、食べたものを吐く、下剤を適正量以上に服用するようになります。この状態が続くと深刻な疾患を招き、最悪の場合命を落とすリスクもあります。早めに医療機関を受診しましょう。
糖尿病
肥満の方が発症するイメージが強いですが、病状が悪化すると体重が減少します。
糖尿病は、インスリンと呼ばれるホルモンの分泌が減少、あるいは働きが低下するため、食事から摂取した糖質をエネルギーとして代謝できず、筋肉多脂肪などのタンパク質を代わりに分解して消費するため、体重減少が起こります。
甲状腺機能亢進症(バセドウ病)
甲状腺から分泌される甲状腺ホルモンは、全身の代謝や成長に関係します。
甲状腺ホルモンの分泌が過剰になると、新陳代謝が亢進し、エネルギーを必要以上に消費するため、体重減少が起こります。一方、安静にしていても激しい運動をしたような状態になるため、心臓などに負担がかかり、多汗や動悸、不眠などの多くの症状を起こします。
こうした症状から、更年期障害や自律神経失調症などと勘違いされることもあります。
一般的な健康診断では正しく異常を検出できないこともあるので、精密検査として血液検査を受けることをお勧めします。
慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍
炎症・潰瘍が発生すると、消化・吸収能力や食欲が低下し、体重減少が起こります。
ピロリ菌感染が原因となることが多く、除菌治療が上手くいけば炎症が治まり、潰瘍の再発を防ぐことも期待できます。また、潰瘍については解熱鎮痛薬(NSAIDs)の副作用により起こることもありますが、処方内容を見直すことで改善が可能です。
潰瘍性大腸炎・クローン病
潰瘍性大腸炎とクローン病は、炎症によりびらんや潰瘍が発生します。
下痢や腹痛、血便が主な症状で、これらの症状に伴って体重減少が起こります。潰瘍性大腸炎は大腸粘膜を中心に炎症が発生しますが、クローン病では口から肛門に至る消化管全域に炎症が及びます。いずれも、症状が治まる寛解期と症状が起こる再燃期を繰り返します。完治させる治療法がないことから、難病指定を受けています。
吸収不良症候群
消化に問題が起こり、胃腸が栄養と水分を適切に吸収できない状態です。
体重減少に加え、むくみや貧血、下痢、脂肪便などの症状を示します。原因は多岐にわたるため、原因を特定するためにも早めに消化器内科を受診しましょう。
胃がん、大腸がん、膵臓がんなど
消化管にがんができた場合、消化吸収機能が低下し、がん細胞が栄養を取り込んでいくため、体重減少が起こることがあります。
また、炎症の場合も食欲不振や体重減少が発生することがあります。体重減少の原因に心当たりがない場合、原因を特定するためにも早めに消化器内科を受診しましょう。
うつ病
うつ病では、食べ物への興味が薄れたり、食欲が湧かなくなったりすることで、体重減少が起こる可能性があります。
早めに専門医に相談し、適切な治療を受けましょう。
体重減少・食欲不振の検査
 問診にて、食欲不振が起こり始めた時期、発生頻度、その他の症状の有無、既往歴などを伺います。また、ストレスや生活習慣の乱れがないかについてもお聞きします。
問診にて、食欲不振が起こり始めた時期、発生頻度、その他の症状の有無、既往歴などを伺います。また、ストレスや生活習慣の乱れがないかについてもお聞きします。
これらの情報をもとに、疾患が原因となっている可能性があれば、血液検査や腹部超音波検査、CT検査、内視鏡検査などを実施します。食道・胃・十二指腸などの上部消化管の疾患の可能性があれば胃カメラ検査を行い、大腸疾患の可能性があれば大腸カメラ検査を実施します。
当院では熟練の医師が検査を担当し、検査による患者様の負担を極力抑えられるように努めていますので安心してご相談ください。
体重減少・食欲不振の治療
 体重減少・食欲不振の原因は様々で、精神的な要因、食道がん・胃がん・大腸がん・膵がんなどの深刻な疾患、脳や心臓疾患の可能性もあります。
体重減少・食欲不振の原因は様々で、精神的な要因、食道がん・胃がん・大腸がん・膵がんなどの深刻な疾患、脳や心臓疾患の可能性もあります。
当院は消化器内科を専門領域とし、精度の高い検査により原因を突き止め、適切な治療を提供します。 消化器疾患以外の原因が疑われる場合、各専門の医療機関をご案内し、患者様がスムーズに治療を受けられるように努めています。また、体重減少が生活習慣の乱れやストレスによって起きている場合、ストレスの解消法、生活習慣の改善に向けてのアドバイス、運動療法などを行います。
体重減少や食欲不振にお悩みの方は、お気軽に当院までご相談ください。