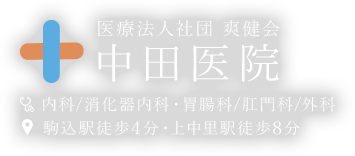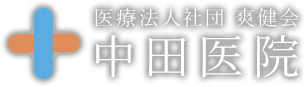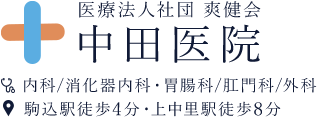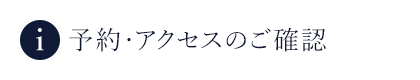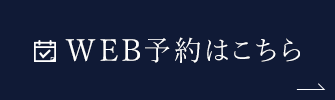逆流性食道炎とは
 逆流性食道炎とは、強酸性の胃酸など胃の内容物が食道に逆流し、食道粘膜にダメージが加わることで炎症が発生する疾患です。
逆流性食道炎とは、強酸性の胃酸など胃の内容物が食道に逆流し、食道粘膜にダメージが加わることで炎症が発生する疾患です。
年齢を重ねて腸の蠕動運動や筋肉が低下することで発症リスクが高まります。また、若い方でも腹部の強い圧迫や生活習慣の乱れ、食習慣などにより発症するケースもよく確認されます。また、逆流性食道炎が原因となるバレット食道も増加傾向にあると言われています。これは、食道粘膜が胃粘膜に置き換わった状態です。逆流性食道炎も食道バレットもがんに繋がる恐れがあるため、定期検診が欠かせません。
食道粘膜の炎症が長引くとがん化リスクが高まります。がんの発症を防ぐためには、食習慣の見直しに加え、専門の医療機関で治療を受けて炎症を改善させる必要があります。
主な症状
- のどの痛み
- のどの違和感
- のどのつかえ感
- 飲み込みづらさ
- 咳
- 声がれ
- 胸痛
- 胸やけ
- 胃もたれ
- げっぷ
- 呑酸(酸っぱいげっぷ)
…など
逆流が発生する原因
逆流が発生する原因は多岐にわたり、よくある原因には下記のようなものが挙げられます。
原因は内視鏡検査により特定可能です。
食道裂孔の弛緩
横隔膜は内臓を支える役割があり、呼吸をする上でも欠かせません。食道は横隔膜にある食道裂孔を通って胃に繋がっています。食べたものはこれらを通って胃へと届けられます。食道裂孔が緩むと、胃液が逆流します。また、胃の一部が食道裂孔から胸腔内に飛び出す食道裂孔ヘルニアが発生している場合、逆流が起こりやすいです。食道裂孔が緩む主な原因は加齢です。
下部食道括約筋の弛緩
食道と胃の繋ぎ目には下部食道括約筋という筋肉が存在しており、食事のとき以外はこの筋肉が胃の入口を閉じているため、逆流が起こることはありません。
しかし、加齢に伴って筋力が低下すると逆流が起こりやすくなります。
蠕動運動の低下
消化管は蠕動運動により内容物を次の消化管へと届けます。
この蠕動運動が低下すると逆流が発生しやすくなります。また、逆流したものを戻す力も弱くなると、食道粘膜が胃液に長時間さらされ炎症が発生します。
腹圧の上昇
腹部を締め付ける服装や肥満、猫背、力仕事、妊娠などにより腹部が強く圧迫されると、逆流が起こりやすくなります。
お薬の副作用
喘息、高血圧、心臓病などの疾患で使われるお薬には、副作用として食道の筋肉を緩めるものがあります。お薬の副作用によって逆流性食道炎が発症していることが疑われる場合、処方内容の見直しが必要です。休薬が難しい場合、炎症を鎮めるためのお薬の服用も必要です。日頃から服用中のお薬がある場合、診察時にお薬手帳、あるいはお薬そのものをお持ちください。
ピロリ菌の除菌治療中
ピロリ菌の除菌治療中の方は、胃酸を分泌する胃粘膜の機能が正常に戻っていく過程で、一時的に逆流性食道炎の症状が起こることがあります。
検査方法
 当院では、逆流性食道炎の検査として胃カメラ検査を行っています。
当院では、逆流性食道炎の検査として胃カメラ検査を行っています。
胃カメラ検査は、食道粘膜を目視で隅々まで観察できます。また、検査中に疑わしい病変が見つかった場合、その場で組織採取を行い、病理検査に回すことで確定診断に繋げられます。
胃カメラ検査は直接粘膜を観察できるほか、バリウム検査と違い被ばくリスクもない点がメリットとなります。
当院では熟練の専門医が検査を担当し、患者様の苦痛を最小限に抑えるために鎮静剤の使用や経鼻内視鏡検査に対応しています。胃カメラ検査について何か分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。
治療方法
逆流性食道炎は、非びらん性胃食道逆流症(NERD)と逆流性食道炎に分けられますが、いずれも酸分泌抑制薬を用いた薬物療法、再発予防のための生活習慣の見直しを行います。治療を行うことで症状は解消できますが、再発予防のためには炎症が完全に落ち着くまで治療を続ける必要があります。
自覚症状が治まったからといって、自己判断で治療を中断してしまった場合、再発とともに食道がんのリスクも高まります。
薬物療法
胃酸分泌抑制薬を中心に治療を行います。また、各患者様の病状によって、粘膜保護薬や消化管機能改善薬を補助薬として使うこともあります。
逆流性食道炎に深刻な食道裂孔ヘルニアが合併している場合、手術を検討することもあります。
治療でよく用いられるお薬
-
プロトンポンプ阻害剤
胃酸分泌を抑制する効果があり、再発予防に有効なお薬です。 -
H2ブロッカー
胃酸分泌に関係するヒスタミンH2受容体に働きかけ、胃酸分泌を抑制する効果があります。ドラッグストアなどでも購入できますが、医師に相談頂くことで、患者様の病状や粘膜の状態に合わせた適切な容量・期間での処方、服用方法をお伝えすることができます。 -
消化管運動機能改善剤
消化管の蠕動運動を改善する効果があります。胃の内部に食物が滞留する時間を短くでき、逆流の発生を抑えられます。 -
制酸薬
胃酸を中和して粘膜を保護する効果があり、仮に逆流が起きても炎症が発生しにくくなります。 -
粘膜保護薬
食道粘膜を胃酸から守ることで、炎症が起こりづらくなります。
生活習慣の改善
腹部が圧迫されるような行動などの改善、胃酸の分泌を促す食生活の見直しなどを行います。再発予防のためには炎症が治まるまで続ける必要があります。
途中で止めてしまわないように、普段から取り組みやすいものから開始することをお勧めします。
食生活の見直し
 甘いものや酸っぱいもの、脂肪を多く含むもの、香辛料などは、胃酸の分泌過多を招くため控えましょう。また、飲酒や喫煙もできるだけ控えましょう。
甘いものや酸っぱいもの、脂肪を多く含むもの、香辛料などは、胃酸の分泌過多を招くため控えましょう。また、飲酒や喫煙もできるだけ控えましょう。
便秘は腸内に便が溜まってしまい、腹圧が上昇するため、逆流が発生しやすくなります。便秘の改善・予防のためにも食物繊維と水分をしっかり摂ってください。腹圧の上昇の要因が肥満の場合、エネルギー摂取量を調整しましょう。
姿勢改善
猫背や前屈みなどが常態化すると、腹部の圧力が高まり、逆流が起こりやすくなります。
姿勢を改善し、腹部を締め付けるような服装を避け、肥満の方はダイエットに取り組みましょう。
睡眠
 食後すぐに横になってしまうと、胃酸が逆流し、胸やけや咳などの症状が起こりやすいです。そのため、食後2時間以上経過してから横になりましょう。
食後すぐに横になってしまうと、胃酸が逆流し、胸やけや咳などの症状が起こりやすいです。そのため、食後2時間以上経過してから横になりましょう。
就寝時、のどの違和感や咳などの症状が起こる場合、背中にクッションを敷き、上半身を少し高くすることで症状の解消が期待できます。
医師の指示に従ってお薬を服用しましょう
 症状の内容や炎症状態、原因を確認した上で、適切なお薬を処方します。
症状の内容や炎症状態、原因を確認した上で、適切なお薬を処方します。
なお、間違ったタイミングで服用すると、効果がしっかり現れないため、医師から指示があった服用タイミングを守りましょう。また、炎症が治まるまでに時間がかかることもあり、自覚症状がなくなったからといって、自己判断で服用を中断すると再発してしまう恐れがあります。医師に指示に従って服用を続けてください。