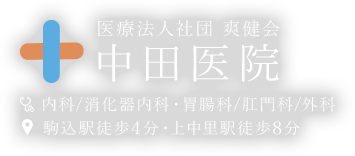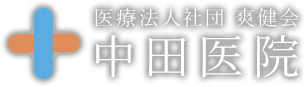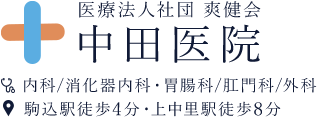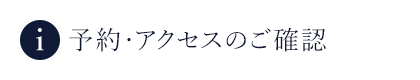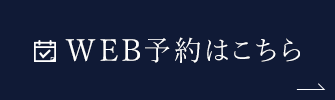目次
お腹の張り・膨満感について
 お腹の張りは「膨満感」とも表現されます。
お腹の張りは「膨満感」とも表現されます。
膨満感は多くの場合、意図せずに飲み込んだ空気や便秘によって起こりますが、腸閉塞など疾患が原因となることもあります。腸閉塞では、急激な膨満感が発生し、激しい腹痛や嘔吐なども起こることがあり、重症化すると命を落とすリスクがある腹膜炎を合併する恐れもあるので、早急な治療が必要です。
また、膨満感のほか、腹痛や呼吸苦、むくみ、食欲不振、発熱などの症状も起こる場合も、早めに消化器内科に相談しましょう。 症状が膨満感のみの場合も、機能性ディスペプシアや過敏性腸症候群などを発症している可能性があります。なお、この2つの疾患も適切な治療を行うことで改善が期待できます。膨満感は日常生活にも影響するので、膨満感で苦しいと感じている、膨満感に伴っておならやげっぷの回数が増えたなど、お困りの症状があれば当院までご相談ください。
膨満感の原因となる主な疾患
便秘
便秘は腸内に便が溜まるので、膨満感が発生しやすいです。原因は、消化器疾患やお薬の副作用など様々なものがあります。また、便秘が長期間にわたって継続すると、痔や大腸疾患の発症を招くことがあります。そのため、便秘が慢性化している方は、原因を特定するためにも消化器内科を受診し、便秘の原因・種類に応じた適切な治療を受けましょう。
当院では、便秘の原因・種類に応じた適切な治療を実施しています。
腸閉塞
腸管の狭窄・閉塞・癒着、大腸ポリープや大腸がん、腫瘍、蠕動運動の低下、血流障害などにより、腸内の内容物が溜まってしまう疾患です。
膨満感や腹部の激痛、吐き気・嘔吐などの症状を示すことが多いです。速やかに治療を受けないと深刻な状態となる恐れがあるので、気になる症状があれば早めに当院までご相談ください。
過敏性腸症候群
大腸カメラ検査などを行っても器質的異常が見つからないにも関わらず、腹痛とともに便秘や下痢、膨満感などの症状が繰り返し起こる疾患です。
消化管の知覚過敏や機能不全が影響して症状が発生するのではないかと言われています。ストレスを受けることで症状が発生することがあり、生活の質も低下するため、早めに消化器内科にて適切な治療を受けましょう。
呑気症
食事中に空気を飲み込んでしまうことは普通ですが、呑気症は意図せずに多量の空気を飲み込み、腹部膨満感が起こる疾患です。
その他、おならやげっぷが頻発するようになります。原因には、ストレスや早食いなどが挙げられます。
逆流性食道炎
胃酸を含む胃の内容物が食道に流れ込み、食道粘膜に炎症が発生する疾患です。
高脂肪の食事などにより胃酸が分泌過多になるため、昨今の食生活の欧米化をきっかけに発症数が増えてきています。呑酸や胸やけ、のどの違和感、つかえ感、咳などの症状がよく起こりますが、膨満感が発生することもあります。代表的な原因は、加齢や食生活を含む生活習慣の乱れです。
また、特徴として再発のしやすさが挙げられます。何度も再発して食道粘膜に発生した炎症が慢性化すると、食道がんに繋がる恐れもあるので、疑わしい症状が続く場合は消化器内科にて検査を受け、再発防止も視野に入れた治療を受けましょう。
急性胃腸炎
胃腸粘膜に突然激しい炎症が発生する疾患の総称です。原因は多岐にわたり、例えば、細菌やウイルスなどの病原体の感染、お薬の副作用などが挙げられます。
主な症状には、腹痛、下痢、吐き気・嘔吐などがありますが、発熱や膨満感などが発生することもよくあります。
機能性ディスペプシア
胃カメラ検査を実施しても器質的異常は見つからないにもかかわらず、胃の不快感や胃もたれ、膨満感、早期膨満感、心窩部痛などの症状が長期間にわたって続く疾患です。原因ははっきりとしていませんが、胃の機能的異常や知覚過敏が影響していると言われています。
また、従来は効果的な治療法がありませんでしたが、昨今は効果的な治療法が確立されています。気になる症状がありましたら、当院までお気軽にご相談ください。
腹部の腫瘍
胃がんや大腸がんなど消化器に発生したがんにより、膨満感が発生することがあります。
女性では、子宮がんや卵巣がんが原因となることがあります。
上腸間膜動脈症候群
十二指腸と症状の繋ぎ目には、大動脈や上腸間膜動脈などの血管が通っています。この血管は周囲の脂肪によって保護されています。
しかし、急激な体重減少により、脂肪が減少すると、十二指腸から血管が圧迫され、膨満感などの症状が発生することがあります。食後すぐに仰向けの状態で横になると圧迫が強まり症状がひどくなります。一方、うつ伏せの状態では圧迫が弱まり症状が落ちつくことが多いです。